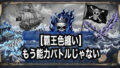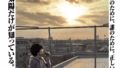閉じ込められた教室、透明な容器に浮かぶ無数の脳、そして「A先生」と名乗る謎の女性――。漫画『群脳教室』は、日常と狂気が紙一重で交差するサイコサスペンスの傑作です。
最初の1話から衝撃的な展開が続き、ページをめくる手が止まりません。作者の緻密な伏線構成と、登場人物の心理描写が読者を圧倒し、気づけば“脳”というモチーフに取り憑かれている自分に気づくはずです。この記事では、そんな『群脳教室』のあらすじや作品情報、ネタバレ感想をたっぷりと紹介します。
【群脳教室】あらすじ
いつもの通学路で警官に呼び止められ、遅刻して教室に入ることになった筒野悟希。だがその教室には、見たこともない「A先生」と名乗る女性が立っていた。
机の上には無数の透明な容器。その中には人間の「脳」が整然と並べられている。突如として校舎全体が封鎖され、悟希たち生徒は脱出不可能な“実験教室”の中で生き残りをかけた授業に巻き込まれていく。
クラスメイトを元に戻すには、脳を通じて「世界の真実」を理解しなければならない。果たしてA先生の目的とは何なのか?そして悟希は“脳”の支配から逃れられるのか――。恐怖と哲学が交錯する、極限の知的サスペンスが幕を開ける。
【群脳教室】作品情報
脳だけになった級友を、そして世界を救うため少年が試練に挑む「群脳教室」1巻https://t.co/XhcgxPYEEQ#ジャンププラス pic.twitter.com/vB13ze2Ymr
— コミックナタリー (@comic_natalie) October 3, 2025
タイトル:群脳教室
著者:市真ケンジ
連載雑誌:ジャンプ+
【群脳教室】ネタバレ感想
密室の中で進む「脳実験」という絶望的な授業
『群脳教室』の面白さは、ただのデスゲームやホラーでは終わらない点にあります。教室という閉ざされた空間の中で、登場人物たちが「知識」「感情」「記憶」という脳の本質を問われ続ける構成が秀逸です。
A先生が提示する課題は、倫理や哲学をえぐるものばかりで、単なるサバイバルではなく“思想の生存競争”が繰り広げられているようでもあります。読者自身も「自分ならどんな選択をするか」と考えずにはいられません。
悟希の覚醒と“学ぶことの恐怖”
主人公・筒野悟希は、物語の序盤ではただの生徒に過ぎません。しかし、物語が進むにつれ、「知る」ことの代償を理解し始め、次第にA先生の思考に近づいていきます。
この過程があまりに恐ろしく、まるで読者自身の“脳”が書き換えられていくような錯覚を覚えます。
「学ぶ」という行為がどれほど残酷なものか――そのテーマが見事に描かれており、読み終えたあとも頭の中で反芻が止まりません。
支配と自由、そして“人間らしさ”とは何か
A先生の言葉の一つひとつは、ただの狂気ではなく、どこか理性的で冷たい説得力を持っています。人間の脳が作り出す幻想や社会構造への皮肉も多く、「脳=支配」「教室=社会」というメタファーが随所に張り巡らされています。
単なるスリラーとして読むこともできますが、深読みすればするほど、“自由意思とは何か”という人類の根源的な問いに辿り着く。まさに哲学的ホラーの真骨頂です。
『群脳教室』は、読む人によって「最高にスリリングで哲学的」とも「難解でついていけない」とも感じられる、まさに“賛否両論型”のサイコサスペンス作品です。ここでは、その「面白いところ」と「つまらないところ」を、物語の構造・キャラクター・テーマ性の3軸から掘り下げて紹介します。
【群脳教室】面白いところ
①「脳」というモチーフで描く知的サバイバルの緊張感
まず何よりも面白いのは、作品全体が“脳”という一点に集約されていることです。教室内に並ぶ透明な容器、そこに浮かぶ生徒たちの脳という異様な光景から始まり、読者は一瞬で物語の異常さに引きずり込まれます。
通常のサバイバルホラーなら「死」や「暴力」による恐怖が中心になりますが、『群脳教室』では「知識」や「意識」をめぐる恐怖が描かれます。生徒たちがA先生に与えられる“課題”を解くたびに、彼らの精神が削られ、壊れていく過程はまるで哲学実験のようで、読者まで試されている気分になります。
「頭が良くないと生き残れない」――そのルールの中で展開するドラマは、これまでのデスゲーム作品とは一線を画す知的スリルを生み出しています。
②A先生というカリスマ的存在
A先生のキャラクターは、『群脳教室』を象徴する魅力の一つです。
ただ残酷な狂人ではなく、彼女には確固とした思想と目的がある。人間とは何か?脳が支配する社会で、自由は存在するのか?その講義のような思想はどこか冷静で美しく、読者を恐怖と尊敬の入り混じった感情に陥らせます。
また、A先生のビジュアル演出も秀逸で、無表情の中に潜む狂気が強烈な印象を残します。彼女の言葉に説得力があるため、読者も次第に“洗脳”されていくような不気味な感覚を味わえるのです。
③人間心理のリアルな崩壊と連鎖
教室という密室の中で、友情・信頼・裏切りが交錯していく構成も見どころのひとつです。誰が本当の仲間で、誰がA先生に操られているのか――その曖昧さが続くことで、読者は常に緊張を強いられます。
とくに悟希が次第に「A先生の理屈」に共感し始める描写はゾッとするほどリアルで、人間の弱さと知的傲慢の危うさを突きつけられます。
「正しさ」を求めて学び続けた結果、人はどこまで壊れるのか。その問いが、ページを閉じたあとも長く心に残るのです。
【群脳教室】つまらないところ
①説明が難解で、哲学的すぎる
本作最大の難点は、会話やモノローグが非常に抽象的で難解なことです。
A先生のセリフや授業の内容は、哲学書のような抽象論や比喩が多く、読者によっては「何を言っているのかわからない」「テンポが悪い」と感じる場面もあります。特に中盤以降は“思想戦”が中心となり、ストーリー展開が遅く感じられる読者も少なくありません。
エンタメ性よりも思想性が前に出ているため、純粋に「物語を楽しみたい」タイプの読者にはややハードルが高い作品です。
②キャラクターの掘り下げが不十分
悟希やA先生以外のキャラクターの描写が浅く、感情移入しづらい点もあります。
脇役の多くは実験のモルモットのように“使い捨て”で描かれ、犠牲になっていく過程も淡々としているため、読者が彼らの死を悲しむ余地が少ないのです。
また、悟希の心理変化は興味深い一方で、「どうしてここまで極端に変わったのか」という描写の積み上げが不足しており、説得力が弱いと感じる人もいるでしょう。
③ストーリーのテンポが重く、終盤に冗長さ
『群脳教室』は緻密に設計された物語ゆえに、一話ごとの密度が非常に濃いです。
その分、読者に“集中力”を強く求める作品であり、テンポよく読める作品とは言い難い部分があります。
特に終盤では、「もう少し話を進めてほしい」と思う場面で哲学的対話が続き、緊張感が薄れる箇所も見受けられます。こうした“難しさ”が、一般的な読者にとっての「つまらなさ」につながっているとも言えます。
【群脳教室】おすすめ読者
思考型サスペンスが好きな読者に
『約束のネバーランド』や『ダーウィンズゲーム』のような、知的駆け引きや心理戦を楽しみたい読者には特におすすめです。単なる恐怖やグロではなく、“考えさせる恐怖”を味わいたい人にぴったりです。
倫理や哲学に興味がある人に
「人間の意識とは何か」「善悪の境界とは何か」といったテーマを掘り下げたい読者に刺さります。A先生の講義のようなセリフ群は、どこか現実社会への痛烈な風刺にも通じており、思わずノートを取りたくなるほどの知的刺激があります。
ダークな学園ものに飢えている人に
『群脳教室』は、表面的には学園ものですが、内容は極めて残酷で絶望的。それでも希望を探す登場人物の姿に心を打たれます。王道の青春ドラマでは物足りない、刺激を求める読者にこそ薦めたい一作です。
コミックス購入はこちら
【群脳教室】最終話や結末話は
漫画『群脳教室』はまだ完結しておりません。
今後、A先生の正体や“群脳”の真の目的がどのように描かれるのか、ますます目が離せません。物語が進むごとに、悟希の精神は壊れていくのか、それとも新たな人類の形へと進化していくのか――。読者の脳を揺さぶり続ける衝撃の展開に期待が高まります。