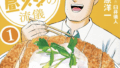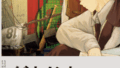「娘がいじめをしていました」という衝撃的なタイトルから始まるこの作品は、読者の心を掴んで離さない社会派ドラマです。いじめの加害者となった娘と、その事実に直面した母親の苦悩、そして周囲の人々の反応がリアルに描かれており、多くの視聴者や読者が考えさせられる物語になっています。
単なる“いじめ問題”の表層だけでなく、家庭環境や親子関係、そして大人の責任の在り方まで深く切り込んでいるため、話題性は非常に高く、ドラマ化配信も大きな反響を呼びました。
特に母親が「娘のいじめ」を知った瞬間からの葛藤と、加害者家族として背負わざるを得ない現実は、視聴者に強い問いを突きつけてきます。
最後まで読むと胸が締めつけられる一方で、いじめ問題の本質や人間関係の脆さ、そしてそれを乗り越えるための可能性に気づかされる深いラストが待っています。これから完結までの展開や結末をネタバレ感想としてお伝えします。
【娘がいじめをしていました】あらすじ
『娘がいじめをしていました』読了。これは良かった。子どもがいじめに加担していたとき親にできることはなんだろうね pic.twitter.com/e5S7EBvd4i
— としょがかり (@NishisDelivery) August 10, 2024
中学時代にいじめられた経験を持つ赤木加奈子はある日、小学5年生の娘・愛が同級生の馬場小春をいじめていることを知り、家族で馬場家に謝罪に向かう。加奈子たちの謝罪はその場では受け入れてもらえたものの、小春はその後、不登校になってしまう。小春の母・千春は苦しむ娘を見て知り合いに相談するが、SNS上での匿名の告発をきっかけに、思いもよらない事態へと発展してしまうのだった──。我が子への不信感、夫との意見の相違、SNSで巻き起こる炎上…様々な問題に翻弄される二つの家族。自分の子供がいじめの当事者と知った時、「正しい対応」とは果たして何なのか?いじめ問題を加害者家族、被害者家族双方の視点から描く、意欲的セミフィクション。
【娘がいじめをしていました】作品情報
娘がいじめをしていました
著者
しろやぎ秋吾
カテゴリ
女性マンガ
出版社
KADOKAWA
レーベル
コミックエッセイ
【娘がいじめをしていました】ネタバレ感想
加害者と被害者「両方の家族」を描くリアルな視点
多くのいじめ漫画は被害者の視点に寄り添って描かれることが多いですが、本作ではいじめた側の家庭と、いじめられた側の家庭を同時に描きます。いじめをした加害者家族の苦悩や罪悪感、そして被害者家族が抱える怒りや絶望。その両方を並行して描くことで、単純な勧善懲悪ではない複雑な人間模様が浮かび上がります。
「謝罪」で終わらないいじめ問題の現実
いじめが発覚した後、加害者側が謝罪をしても被害者側の傷は癒えず、むしろその後の不登校や家庭内の亀裂にまで発展していく様子が描かれます。作中では「謝ったらそれで終わり」では済まない現実が強調され、いじめの根深さや後遺症が生々しく突き付けられます。
SNS時代ならではの“二次被害”
匿名の告発によって加害者の顔写真や動画が拡散され、炎上に発展してしまうという要素も本作の大きな特徴です。現代のいじめは学校の中だけで完結せず、ネット社会で容易に「晒し者」になってしまう。その加害者家族の苦しみや、ネットリンチの恐ろしさが重くのしかかってきます。
親子の関係が揺らぐ心理描写
赤木加奈子は自身がいじめ被害を受けた過去を持ち、その娘がいじめ加害者になっていた事実を受け止められません。母親として愛を守りたい気持ちと、いじめ加害者として嫌悪してしまう気持ちの板挟み。この揺れ動く心理描写が非常にリアルで、読者も「もし自分だったら」と考えざるを得なくなります。
正解のない問いを投げかける物語
いじめ加害者を徹底的に糾弾することが正しいのか、それとも更生の機会を与えるべきなのか。被害者家族の怒りは正当でありながらも、社会全体が加害者を叩き続けることで別の歪みも生まれる。作品はどちらの立場にも偏らず、読者に「自分ならどうするか」と問いかけ続けます。
読み終わった後に残る重い余韻
最後まで読んだあともスッキリとした解決はなく、むしろもやもやや苦さが残ります。しかしそれこそが本作の魅力であり、リアルな問題提起型の作品としての存在意義です。いじめは誰も幸せにしないという厳しい現実を、じわじわと実感させられるのです。
この見どころをまとめると、ただの「いじめ漫画」ではなく、親として、あるいは子を持つ読者としても突き刺さる社会派ドラマに仕上がっていると言えるでしょう。
【娘がいじめをしていました】おすすめ読者
子育て中の親世代
自分の子供がいじめの「被害者」になるかもしれないし、逆に「加害者」になってしまうかもしれない。どちらの立場も描かれるこの作品は、子供を持つ親にとって決して他人事ではありません。日常の会話や態度から、子供の心の変化にどう寄り添うかを考えさせられます。
教育や学校現場に関わる人
教師やスクールカウンセラー、教育関係者にも大きな示唆を与える内容です。加害者・被害者双方の家庭が抱える葛藤を知ることで、学校内での対応だけでなく、保護者への支援や連携の難しさについても理解を深められます。
SNSの影響に関心がある人
現代のいじめは学校内にとどまらず、SNSで一気に拡散し炎上する時代になっています。ネットリンチや個人情報の晒しといった“二次被害”がリアルに描かれているため、ネット社会の危うさに問題意識を持っている人にも強く響くでしょう。
人間ドラマを深く味わいたい読者
勧善懲悪のスッキリする物語ではなく、答えのない問いを突きつけてくる重厚な人間ドラマが好きな読者にぴったりです。母と娘、夫婦、保護者同士など、多層的に揺れ動く人間関係がリアルに描かれ、読後に深い余韻を残します。
社会問題に関心のある人
いじめというテーマは一つの家庭の問題にとどまらず、社会全体に関わる課題です。匿名性の高いSNSの拡散、保護者会での責任の押し付け合い、そして「正しい対応」とは何かという普遍的な問題提起。社会派作品を好む人にとって、必ず考えさせられる読書体験となるはずです。
この漫画は、いじめをテーマにしながらも「家庭」「社会」「ネット」という多層的な問題に切り込む作品なので、幅広い層の読者に強く訴えかける力があります。
【娘がいじめをしていました】ネットの声

漫画だけど、過度なストーリーではなく、とてもリアルないじめを描いた作品です。自分の子供がイジメられた時と自分の子供がイジメる側になった時に、親としてどう対応していくのが正しいのか、難しい問題だなと感じました。

この作品の中では、普通の家庭で両親に愛されて育った少女がいじめをしています。我が子がいじめられた親が悩み傷つくのと同じように、我が子がいじめをしていた親も悩み傷ついています。ごく一般的な人たちが加害者にも被害者にもなるからこそ恐ろしいのだと改めて気づかされます。

自分の子供がいじめられた・・・という話は、よくありますが本作は、いじめた側の話。というか、いじめ加害者・被害者双方の親がW主人公といっていいような話。それぞれの視点で物語がすすむので、双方の状況や言い分がわかるのが、本作の特徴です。
コミックス購入はこちら
【娘がいじめをしていました】最終話や結末話は
赤木家のその後
愛がいじめの加害者として世間から晒され、SNSで顔写真や動画が拡散されたことで、赤木家は家庭ごと標的になります。学校だけでなく家や父親の職場にまで嫌がらせが押し寄せ、ついに一家は引っ越しを余儀なくされます。
母の加奈子は、自分が愛を守らなかったせいで娘が第三者から暴力を受けたと強く後悔します。幸い命に関わるような怪我ではなかったものの、その出来事は家族に大きな影を落としました。加奈子は「誰からも許されなくても、この子を一人にはしない」と心に誓い、娘と共に罪を背負っていく覚悟を決めます。
馬場家のその後
不登校が続く小春に焦りと苛立ちを募らせていた母・千春は、他の保護者たちと連携し赤木家を糾弾しますが、やがて「結局みんな自分を守ることしか考えていない」という現実に気づきます。保護者会は「いじめをどうするか」ではなく「誰が動画を撮ったのか」という犯人探しにすり替わり、千春は虚しさを覚えるのです。
本当に向き合うべきは小春自身の気持ちだと悟った千春は、娘に「ごめんね、話を聞いてあげられなかった」と謝罪。二人の間に少しずつ新しい信頼関係が築かれていきます。
愛と小春の手紙
愛はどうしても小春に気持ちを伝えたいと手紙を書きます。加奈子は葛藤しながらも馬場家へ手紙を届けに行きますが、千春は受け取りを拒否。それでも破り捨てられることなく下駄箱の上に置かれました。
物語のラスト、赤木家の引っ越し当日に小春から返事の手紙が届きます。そこにははっきりと「許せない」という言葉が書かれていました。手紙を読んで号泣する愛の姿を見て、加奈子は「世界中の誰も許してくれなくても、この子を絶対に一人にはしない」と改めて心に誓います。
終幕に込められたメッセージ
いじめに「解決」という言葉は存在せず、被害者にも加害者にも消えない傷が残ります。償いとは一生かけて背負うものだと描かれるラストは、加害者家族も被害者家族も決して幸せになれない現実を突きつけます。
いじめは「誰も幸せにしない」。この作品が最後に読者に残すのは、その厳しすぎる現実でした。
▼アニメを見るならここ▼

▼あわせて読みたい▼